電話消毒薬普及とその背景
電話機受話器に付着していた細菌数の割合は、送話口54%・受話口32%・取っ手14%の順でした。
送話口は、唾液、時にはタバコのヤニが混じり合って、細菌が付着しやすく、その数は1万個位でした。
その多くは健康な人には害のない細菌ですが、中には病原菌や日和見感染症の起因となる弱毒菌も
認められました。
送話口の表面は栄養分がないので、付着した細菌がそこで増殖することはありませんが、ある期間は
生き続けます。普通大人1回の呼吸で500ml位、丁度小ジョッキ1杯分の分量の空気を吸い込むといわ
れており、通話の際に送話口が媒介となって、病原菌や弱毒菌が口や鼻から入りこみ、呼吸器の疾病の
原因となる可能性は否定できないことから、潜在的に気がかりを感じるものと思います。
また、送話口には通話口と呼ばれる小さな穴があり、その内部はいろいろな細菌が存在していることが
推測されます。通話の際にこの細菌がどのような動きをするのか調べたところ、呼吸している程度の送風
によって外部に拡散することが分りました。このような状況から、常に快適な通話を求めるには何らかの
手だてが肝要となります。
昭和27年、送話口を消毒する製品は、薬事法に基づき、人の疾病予防の範疇として“電話機送話口の
消毒に使用されることを目的”とする「医薬品」となりました。
この医薬品は便宜上「電話消毒薬」と呼称することになりました。
当時は結核が国民病といわれる程に蔓延し、国は結核の撲滅と予防を最重点課題として取組み、国民
に結核についての啓蒙と意識の向上に努めていたことで、電話消毒薬は結核菌を殺菌する成分を配合し
ているため、世間に認められ認知されるようになりました。
電話消毒薬は要・不要のモノとしての問題ではなく、常に消毒されているという清潔感と安心感が無意識
のうちに必要性を生み、評価をいただいて定着しました。
(当社研究室室長)
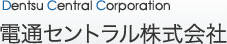

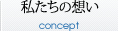
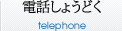
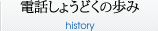


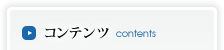
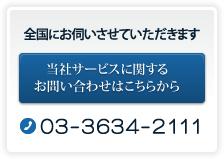
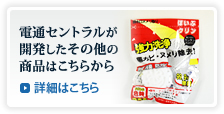



.jpg)
