燻煙で殺菌・防腐効果
食材の保存性を高める方法の一つに“燻す”があります。
いわゆる“燻製”にするという方法です。
まずは塩漬けにすることで、浸透圧により、その食材の水分が排出されます。これによって食
材中の水分が少なくなり、雑菌が繁殖しにくい環境になり、殺菌効果ももたらしてくれます。
その後、塩抜きして乾燥させ、木片(チップ)を燃やした煙で燻し、風味付けなどをします。
燻す煙には、食材を殺菌、防腐する成分が含まれており、保存期間を延ばす効果が得られます。
この煙を燻煙といいます。
燻煙に含まれる殺菌・防腐成分の代表的なものとして、フェノール系化合物やホルムアルデヒ
トなどがあります。
フェノール系化合物は、食品に反応して表面に固い樹脂膜を作りコーティングします。それに
よって、細菌の侵入を防ぐという防腐効果を発揮します。
他にも煙の中には、カルボニル化合物や有機酸類が含まれており、風味や香味に影響を与えま
す。
カルボニル化合物は、ほのかな渋みと苦味などが生み出す深い味わいに大きく関係していると
いわれています。
燻製と一言にいっても、作る食材によって温度設定や煙をかける時間が変わり、3種類に分け
られます。
・冷燻法 貯蔵が主目的 15~30℃ 1~3週間
(骨付きハム、ベ-コン、ドライソーセージなど)
・温燻法 調味が主目的 50~80℃ 1~12時間
(ボンレスハム、ロースハム、ソーセージなど)
・熱燻法 調味が主目的 120~140℃ 2~4時間
(釣った魚、チキン丸ごとなどをその場で調理)
保存性を高めるためには、低めの温度で燻す時間を長くする冷燻法が適しています。
燻製の歴史は非常に古く、ベーコンは紀元前に原型ができ、ジャーキーはアメリカ発見の前から
インディアンが食べていたとされています。
日本では、秋田県の漬物「いぶりがっこ」は、室町時代に誕生したそうです。
その頃は、雑菌の繁殖という意識はなかったと思われますが、こうすれば腐らないという保存法
を発見していることに驚きます。

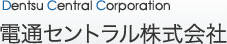

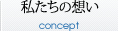
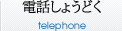
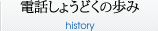


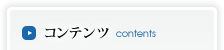
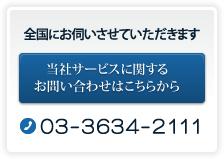
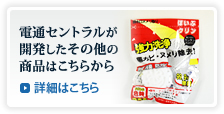



.jpg)

トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.cleall.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/199